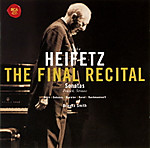「ラスト・リサイタル」 ヤッシャ・ハイフェッツ
BVCC-37127/8
ラスト・リサイタル ハイフェッツ
フランク:ヴァイオリン・ソナタ
R.シュトラウス:ヴァイオリン・ソナタ
J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番より
ブロッホ:組曲「バール・シェム」 第2曲 ニーグン
ドビュッシー(ロック編):レントよりおそく
ラフマニノフ(ハイフェッツ編):練習曲「音の絵」変ホ長調op.33-4
ファリャ(コハンスキー編):「7つのスペイン民謡」第5番 ナナ (子守歌)
クライスラー:カルティエのスタイルによる狩り
ラヴェル:ツィガーヌ
-アンコール-
テデスコ(ハイフェッツ編):海のささやき~二つの海の練習曲より
ヴァイオリン:ヤッシャ・ハイフェッツ ピアノ:ブルックス・スミス
録音:1972年10月23日 ロサンジェルス ドロシー・チャンドラー・パヴィリオン でのライヴ
これは教鞭をとっていた南カリフォルニア大学音楽部の学生と教授陣の勉学の資金調達の為に1972年10月23日にひらいた慈善コンサートのライブ録音で、公開のコンサートとしては最後のものとなったリサイタルになります。
晩年のハイフェッツは持てる時間のほとんど全てを若手の指導に注いでいて、公開の演奏会からはほぼ完全に遠ざかっていたそうですが、これは10年ぶりに開いたリサイタルということです。
ハイフェッツは1901年2月生まれということなのでそのとき71歳ということなのですが、前半に大きなソナタを弾き後半にはヴィルトゥオーゾピースを交えた小品集を弾きこなすという離れ業をやってのけます。
フランクもシュトラウスも過度にロマンティックな表現に陥ることなく、、しかし決して冷徹な醒めた演奏ではありません。作品の本質を鋭くえぐり出すすぐれた解釈、演奏と言えるのではないでしょうか。
その後の小品集は、まさにハイフェッツの自家薬籠中のものと言えるでしょう。クライスラーで聴かせるスピッカートの切れ味はハイフェッツならではのものです。
さすがに最後のツィガーヌではスタミナが切れたのか、それとも時間的にさらいたりなかったのか、ハイフェッツとしてはかなりあやしいところのある演奏。しかしそれはそれで、ハイフェッツもやはり人の子だったのだとちょっと安心させてくれますね。
ハイフェッツが最後に到達した境地、そして若い頃から少しも変わっていない曲の構成力、聴衆を引き付ける求心力等を聴くにはまたとないCDでしょう。
録音は聴衆のノイズも含めた大変生々しいもので、このコンサートを固唾をのんで皆が聴き入る様が手に取るようにわかります。貴重なドキュメントの記録としても一聴をお薦めいたします。

 045-989-1599
045-989-1599